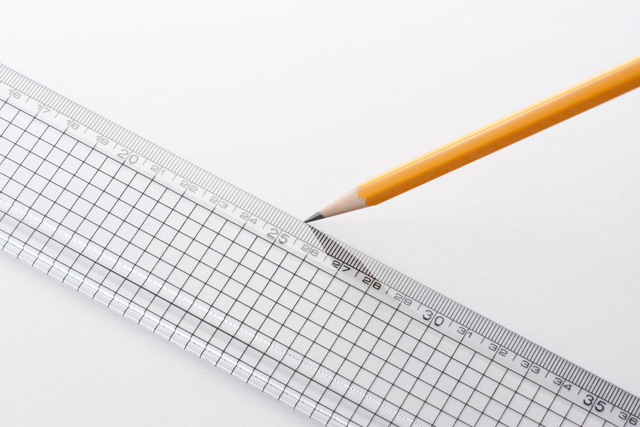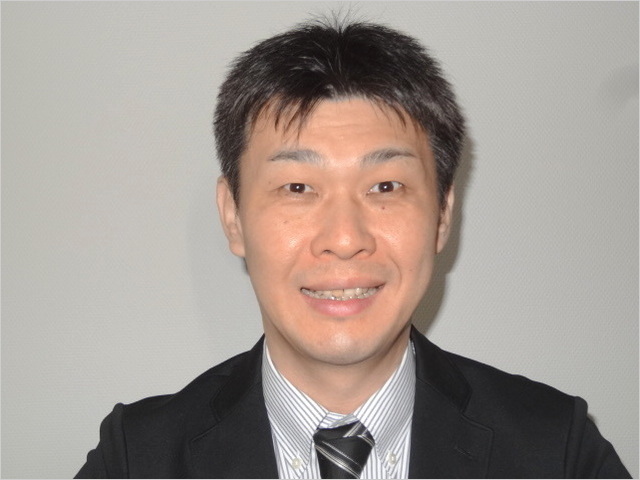運営:行政書士まつもと事務所
建設業の皆様のパートナー!
出張無料相談実施中
土日祝も対応いたします。
080-2414-8898
受付時間:8:00~20:00
06-6940-4870
建設業許可の制度

建設業の許可は、元請け人、下請け人に関わらず建設業法第3条に基づいて一般建設業、特定建設業の許可区分により国土交通大臣、都道府県知事から建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な工事のみ請負う建設業者は、許可を受けなくてもよいとされています。
具体的に軽微な工事とは、建築一式工事では1件の請負額が1,500万円未満(税込)の工事、木造で延べ面積が150㎡の工事の場合や、その他の専門工事では1件の請負額が500万円未満(税込)の工事では許可を受けなくても工事を請負うことができます。
大臣許可と知事許可

建設業の許可は、国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の2種類があります。どちらの許可を取得するかは、営業所の設置状況によって決まります。
 大臣許可
大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を開設して営業する場合の許可です。
例えば、大阪に本社があり、兵庫県に支店がある場合は、大臣許可を取得することとなります。この場合は、本社・支店の両方に専任技術者を配置する必要があります。
 知事許可
知事許可
1つの都道府県内の営業所のみで営業する場合の許可になります。
1つの都道府県内であれば、複数の営業所があったとしても、知事許可となります。
例えば、大阪に本社があり、兵庫県に資材置場などの倉庫がある場合は、知事許可を取得すれば良いこととなります。
また、仮に大阪府内に3カ所営業所があったとしても知事許可となります。
知事許可であっても、他の都道府県で工事を請け負うことは可能です。
 営業所とは、常時請負契約の締結を行う本店や支店などのことを言い、登記上のだけの本店や、現場事務所などは営業所に該当しません。
営業所とは、常時請負契約の締結を行う本店や支店などのことを言い、登記上のだけの本店や、現場事務所などは営業所に該当しません。
特定建設業許可と一般建設業許可

建設業の許可は、特定建設業許可と一般建設業許可の2種類に区分されます。
 特定建設業許可
特定建設業許可
発注者から直接請負う1件の建設工事につき、下請人に施工させる金額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円)となる者が受ける許可です。
これは、複数の下請業者に施工させる場合でも、複数の下請金額の合計が5,000万以上(建築一式の場合は8,000万円)となる場合は、特定建設業の許可が必要となります。
特定建設業許可を取得すると、下請けに出す金額に制限が無くなる点がメリットとなります。ただ、下請け業者に対する支払条件等に関し、一般建設業許可に比べて多くの規制がされたり、実務上の負担も増えてきます。
特定建設業の基準となる5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)には、元請人が提供する材料等の価格は含みません。
 一般建設業許可
一般建設業許可
工事の請負金額が、500万円以上(建築一式の場合は1,500万円以上)の場合に許可が必要となります。
下請に施工させる金額が5,000万円未満(建築一式の場合は8,000万円未満)の場合は、一般建設業の許可で問題ありません。
建設工事の種類と業種

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ29の業種が定められています。
2つの一式工事は、大規模な工事を元受業者として総合的に行う建設業者向けの許可です。
また、一式工事の許可を受けた建設業者が、他の27の専門工事を単独で請負う場合は、その27の専門工事の許可を受けていなければならないこととなっています。
ただし、本体工事に付帯する工事については、付帯工事として本体工事と一緒に請負う事が出来ます。
 27の専門工事
27の専門工事
①大工工事 ②左官工事 ③とび・土工・コンクリート工事 ④石工事 ⑤屋根工事 ⑥電気工事 ⑦管工事 ⑧タイル・れんが・ブロック工事 ⑨鋼構造物工事 ⑩鉄筋工事 ⑪舗装工事 ⑫しゅんせつ工事 ⑬板金工事 ⑭ガラス工事 ⑮塗装工事 ⑯防水工事 ⑰内装仕上工事 ⑱機械器具設置工事 ⑲熱絶縁工事 ⑳電気通信工事 ㉑造園工事 ㉒さく井工事 ㉓建具工事 ㉔水道施設工事 ㉕消防施設工事 ㉖清掃施設工事 ㉗解体工事
以上が27種の専門工事になります。
各内容や例示についてはお気軽にお問合せ下さい。
29業種について詳しくはこちらをクリック
許可の有効期限

許可の有効期限は、5年間となります。
期限の日が日曜日などの休日であっても、その日をもって満了となりますので注意が必要です。
引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに更新の手続きが必要となります。
期限が過ぎてしまうと許可が失効してしまいます。一度、失効してしまうと再度取得するには、新規申請をする必要があります。
3ヵ月前から更新申請は可能ですが、限られた期間の中で更新手続きを行う必要があります。
許可申請のポイント
許可申請をご検討中の方は、下記内容もご覧下さい。
お問合せ・無料相談はこちら

お気軽にお問合せください